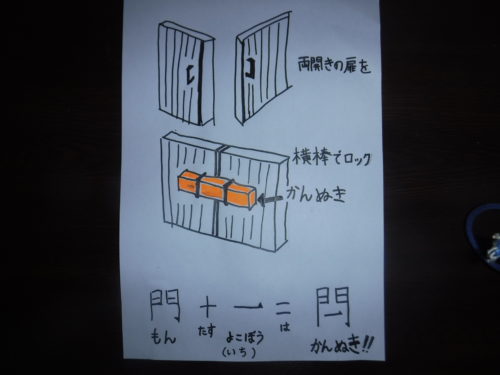ここ3回の出漁で4人、アカエイに刺されました。
毎年誰かしら刺されるものの、短期間に4人も刺されたのは初めてです。
別に例年に比べ格段にアカエイが多いという訳でもないのに、何故なのか?
考えてみると、刺された4人のうち2人は今年の4月に入った新人だし、他の2人は今までに刺されたことがなかったので、エイに対する警戒心が薄かったのかもしれません。
刺された新人の一人が言いました。
「最初、他の人が刺されて痛がっているのを見た時、内心、ちょっと大げさに痛がりすぎじゃないの?と思っていました。
しかし自分が刺されて、その痛みがよくわかりました。」
もう何回も書いてますが、アカエイの毒はほんとに痛いのです。
4人のうち1人は手をやられ、3人は長靴ごしに足を刺されました。
エイの鋭い毒針の前では、長靴の2mm程度のゴム厚など紙切れも同然なのです。
アカエイは増加傾向にあり、今後も網に入ってくるのは確定事項なので、なにか防御策を考えねばなりません。
エイに刺されるパターンで一番多いのは、足元にいるのに気づかずに踏んでしまい、攻撃されるというものです。
エイを踏んでしまうと、その瞬間に尻尾が跳ね上がって毒針を刺されます。攻撃される場所は、すね、ふくらはぎ、足の甲、足の甲の両サイドなど、ほぼヒザから下のあらゆる部分が狙われます。
私達が普段使っている長靴は難なく貫通される為、なにか、プロテクター的なものが入っている長靴が売っていないか探しましたが、あるのは、つま先のみを防御する安全靴だけでした。
そりゃまあそうですよね。「アカエイの針を防御できるような、全体が固い長靴」なんて、需要が少なすぎて商売にならないでしょう。
ときに、どのような材質でどれほどの厚みであれば毒針を防げるのか、私が持っている針で色々なものを刺して試してみました。
この針は座布団くらいの大きさのエイのものです。
写真を撮ったのは実験を終えてからだったので、先端が欠けてしまっています。ほんとはもっと鋭いです。

プラ板0.3ミリ(クリアファイル) 難なく貫通
ビールのアルミ缶 余裕で貫通
牛皮手袋 垂直に刺すと貫通
4ミリ厚の皮 刺さらない
コーヒーのスチール缶 針の先端が折れた
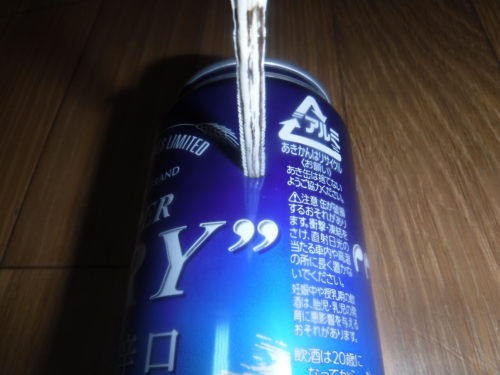

皮手袋が簡単に貫かれたのは予想外でした。
斜めに当たると力が流れて刺さらないのですが、垂直に刺すと軽い抵抗の後、ブスッと刺さりました。
まあ結果としては鉄板が最強ということでした。
鉄製の長靴があればエイに刺されることはないでしょう。
しかしそんなものはありません。あったとしても海じゃ錆びるし。
次点で効果が高かった厚い皮。
カウボーイが履いているような、ヒザ近くまであるような革製のブーツは、防御力が高そうです。
でも考えてみたら、皮って濡れると柔らかくなるんですよね。なんかこれも貫通されそうです。
後はまあ、スキーの時に履くようなごついブーツとか。あれなら毒針も弾いてくれるでしょう。
しかし、機動性は最悪だなあ。
かように個人的に色々と昔から考えてはみるのですが、なかなかうまい対策がおもいつきません。
かくして今宵もまた、東京湾のどこかで、エイに刺された漁師の悲鳴が響き渡るのでしょうなあ。
レ・ミゼラブル!!(邦題「ああ!無情!」)