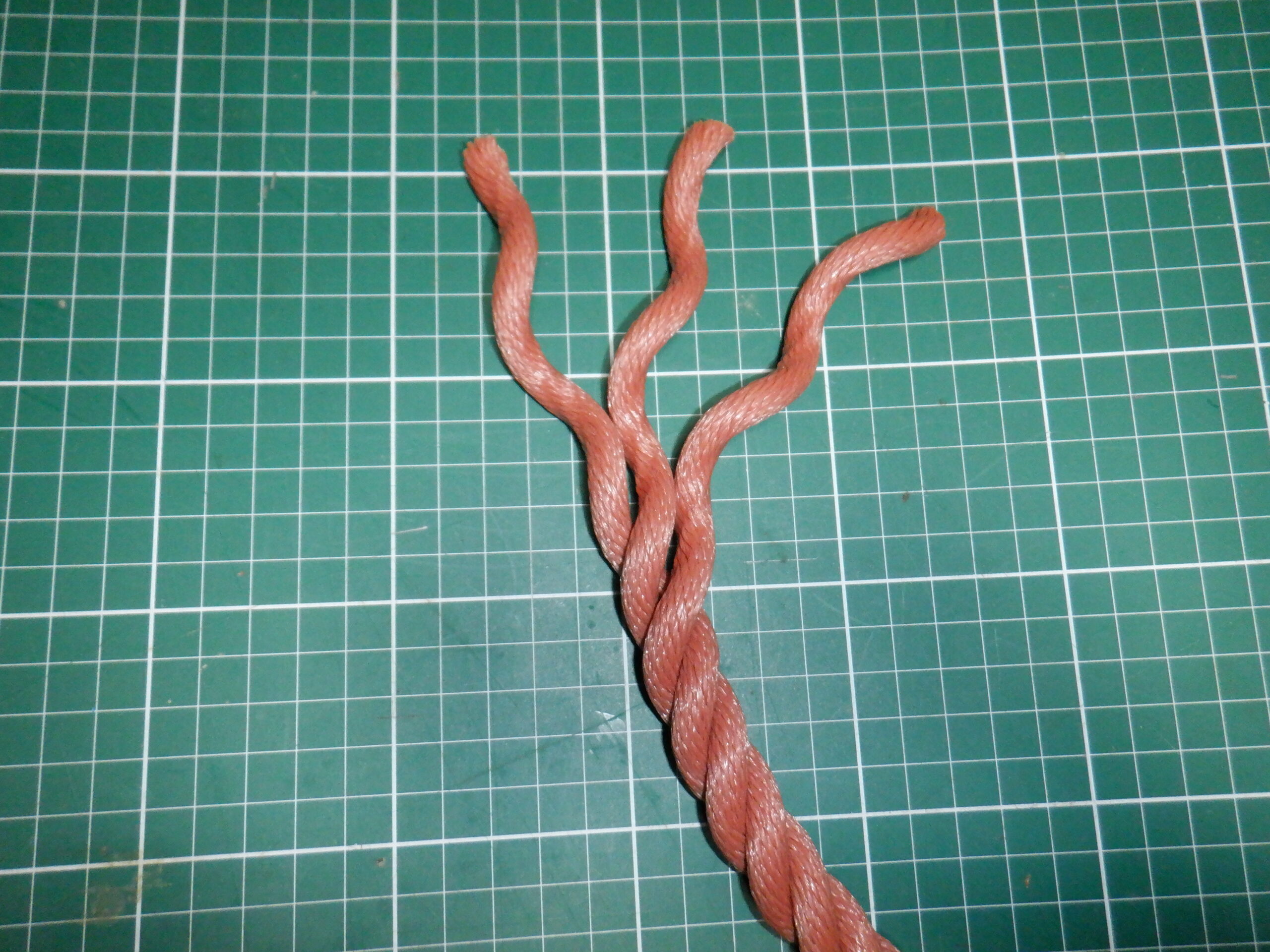網船のエンジンにトラブルがおきてしまい、出漁できません。
これから稼ぎ時真っ盛りなので早く修理せねばと気がはやりますが、機械屋(エンジンメーカーや修理業者の人を私達はこう呼びます)の都合もあり、すぐさま復旧というわけにはいかず、もどかしいです。
機械屋に来てもらうまで乗組員は各自、自分のできる仕事をします。
私は船の網を補修することになりました。
補修をするにあたって、これからの時期はちょっと大変なことがあります。
網がくさいのです。
私達は今、スズキとコハダを狙って漁をしています。
コハダのような小型魚は海中から網を揚げる際に、網にくるまってしまって取り除けず、網の中に残ってしまうものがあります。
それがこの暑さで腐ってしまい、悪臭を放つのです。
写真ではわかりづらいと思いますが、黒い網に白いシミがついているのがわかるでしょうか。
これは腐った魚を取り除いた後に残ったシミです。
網を補修するにはこれに触れねばならないのですが、このシミ程度でもとにかくくさいです。
そしてこのにおいは、付着するとなかなか落ちません。
網仕事を終えた後、せっけんや台所洗剤を使い手を念入りに洗います。
しかし丁寧に洗ったつもりなのに手を嗅ぐと、いくらか軽減されている程度でにおいは消えていません。何回か手洗いを繰り返して、最終的にほんのりくさい程度で諦める、というレベルでなかなか消えないにおいなのです。
このにおいを消すにはどうすればいいか調べたところ、魚の腐敗臭のもとはトリメチルアミンというアルカリ性の物質であり、それは酸性のお酢で中和できるという結論に至りました。
実際にお酢で手洗いを試したところ、台所洗剤では落としきれなかったにおいが消えました。
調べてみるまではお酢で手を洗うなんて考えたこともありませんでした。
お酢は、コハダの酢締めはもとよりコハダの消臭までしてくれるなんて、素晴らしい調味料です。