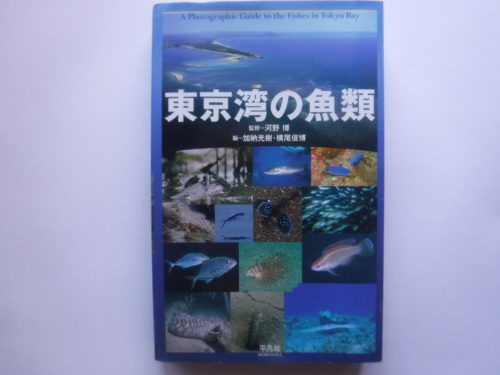寒いですね。
東京湾も冬の海の様相を呈してきました。
私の漁師カレンダーでは今は、コノシロが獲れる、獲りたい時期です。他に良い稼ぎになる魚なんて、イワシが偶然回遊してくるくらいしかいない、というのが私の経験です。
と言ったものの、数年前からサワラや太刀魚の群れがどんどん北上してきて、ここ最近は湾内最奥部でもかなり獲れており、今の時期でもまだ獲れます。
色んな釣りブログやYouTubeなどでもこの情報が広められており、浦安沖あたりでは釣り船やプレジャーボートが今までみたことないくらいひしめきあっています。
11月になってから2回、コノシロのみを狙って漁に出ました。
結果は1日は運搬船が満船になるほど獲れましたが、もう1日は外れでした。
外れとは数トン程度しか獲れず、手間の割にはたいして稼ぎにならなかったということです。
コノシロ漁は、中途半端な量しか獲れないと手間だけかかってあまりメリットがないのです。
今の時期、湾内にコノシロの絶対量は多いのは間違いありません。しかしコノシロの群れの大きさや居場所は様々な要因で変化するので、出漁すれば大量に獲れるわけではないのです。
まあつまり、サワラやコノシロなど、魚は居るにはいるのです。
しかしこの両方が同じ漁場にいた場合、どちらを狙うべきか、これがちょっとした悩みどころなのです。
過去にも書きましたが、サワラが大量に獲れると、網を穴だらけにされてしまうのです。
コノシロは小さく、サワラでは抜けない穴からもどんどん出て行ってしまいます。
サワラを獲ったあとの網ではコノシロをまともに獲れないのです。
では実際に網を見てもらいましょう。

分かりづらいかもしれませんが画面全体に網が広がっています。そしてこの、ところどころ見える赤いスジみたいなものが、補修した箇所です。
拡大するとこんな感じ。
サイズ比較用に置いてある長靴は26センチです。

そして、この補修の糸を取り除くと、こんな大きさの穴になります。

穴の大きさはせいぜい10センチほどですが、スズキやサワラなど大きな魚でも、頭からスルンと抜け出てしまいます。

サワラにはこんな穴を次々と開けられてしまいます。
本当は網の穴は「きおり」という技術でちゃんと網の目を作って直さねばいけないのですが、キオリは時間がかかるので、海上では「沖セバ」という応急の補修をするのみです。
写真のこの網は魚を最終的に追い込む「りょうどり」という場所に使われているもので、他の部分より太い糸で作られています。
それでも、サワラが入ればあっというまにボロボロにされてしまいます。
しかし、サワラだけを相手にするなら、ボロボロの網でもなんとかごまかせるのです。
サワラは各個体が大きいし、一回の網で多くても数百キロしか入らないので、大きな穴さえ沖セバでふさいでおけばそこまで大量には逃がしません。
問題なのは、この状態の網に大量のコノシロが入った場合なのです。
魚が数十トン単位で入ると網の目への負荷は大きくなるので、沖セバで大雑把に直したところは破損しやすくなります。
そして沖セバが弾けた箇所からは、小さいコノシロは怒涛のように逃げていきます。
つまりコノシロを狙う網には、沖セバはあってはならないのです。
出漁してどの魚を狙うべきか、ほんとに親方(おきえ)の判断は難しいです。
今回の記事の参考に「きおり」と「沖セバ」の写真を撮りました。
同じ大きさの穴が二つあり、これを直します。


左がキオリ、右が沖セバです。
キオリは元と同じ網になるけれど、沖セバは無理やり左右を引っ張ってくっつけているのがわかるでしょうか。これは「つれる」という状態で、この部分の強度はがた落ちです。
まあまたの機会に詳しく書きたいと思います。
番外編
このキオリと沖セバの写真のために港で網を広げてました。
ちょうどキオリが終わった時に、野生の獣に襲われました。

獣は私の腹に散々アタックした挙句、網の上にどかっと居座りました。

私「こら。邪魔だ。どきなさい」ペシッ

猫「にゃーん」ペロペロ
うむ、言葉が通じない。しょせん獣だな。
どかないので、無視して沖セバをしました。

めっちゃ見てる。
なかなか勉強熱心だなお前!